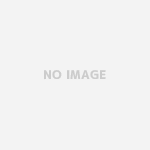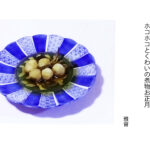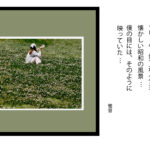動くものにはなぜか目がいく
ブラブラと歩いていたら
ヒラヒラと蝶々が飛んできて
道路脇の花壇の黄色い花にスット留まって…
これは撮らないわけにはいかないよね…
首にかけたスマホを外し
スット近づいてパシャンと一枚

なんだか、渋くて美しい紬の着物を見ているよう
調べてみると
この模様ウラナミシジミというらしい
漢字で書くと
裏波小灰蝶と書くらしい
秋の蝶の代表的なものらしい
しかし、季語にはなっていない
僕にはどうも、季語の基準というものが分からないのだけれど…
これも調べてみた。
ある言葉が季語として機能するためには、以下の条件を満たす必要がある。
季節感があること
文字数が多すぎないこと
そして最も重要なのが、季語の機能を理解すること
(これは分からない)
それが最も重要な要素と言われてもね…
では季語はいつできたのだろうか
調べてみると、
万葉集のできた頃から季節と詩歌の関係が深くなり
季語というのが成立したのは平安時代の後期かららしい
能因歌枕
(歌人が和歌をつくったり、学んだりする際、座右に備えて参看されたもの因能とは姓のこと、清少納言の血縁らしい)
では、月別に分類された150の季語を見ることができると、
そしてその後、
鎌倉時代に連歌
(二人以上の人が、和歌の、上(かみ)の句と下(しも)の句とを互いによみ合って、続けて行く形式の歌)が成立すると、
複数いの参加者の間で、
「連想の範囲を限定する必要性」から
かならず季語をいれなければならないという約束ごとができたということらしい」
しかし、素人の私には、説明をいくら読んでも、よくわからない
ようするに、
遊びとして成立させるために作られたルールなのだと思うが、
その中に季節感を感じさせることができれば、
季語なんか、いらないのではと思ってしまうのだがそういう意味では、
僕は、
山頭火の自由句とか、
リズムで表現する1行詩の方が面白いと思っているのである
だって季語で5文字とられれば、12文字
これで何をだよね…
それにしても芭蕉 蕪村 一茶 良寛
あの宇宙観 の素晴らしさ…
心情 言葉 宇宙観…
意識はしてるんだけどハハハ…