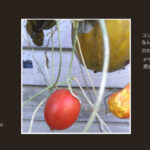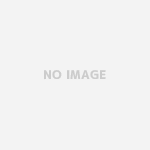目次

唐室、深大寺植物園の展示室で、撮ったもの
資料によると(展示品)
土蔵や穴蔵の利用に冬越しの技術、
やっぱりそれでは、何かやっぱり不満があったんだろうねぇ、
18世紀に「唐室」が発明されて、大きく進歩したと。
ヘー、これ、発明品なんだ。
ということは、例えば蘭など、冬をいかに乗り切らせるかということにとに、頭を使ったんだね、
で、風を避けるために、あるいは少しでも暖かいところへということで、土蔵や穴蔵などに置いていたのだが、何かいい方法がないかと考えたんだね、
で18世紀、天命の頃(1781~1789)に、四谷の住人、朝比奈という人が工夫して作ったのが写真の唐室で、舶来の植物を栽培するのに用いたのが始まりと。
情報、昔も今も
この唐室が世に知られたのは文化15年(1818)に刊行された、岩崎灌園著の「草木育種」という栽培手引書で、「塘窖ぬりだれの事井図」(むろ あなぐれの事井図)。
そこには、唐室の設置理由、制作、使用方法が以下(平野恵氏による現代語で)次のように書かれていると。
江戸時代の園芸文化が伝わってくる
長いので掻い摘んで紹介する。
我わが国(日本)の北方など、寒いところで、インド、ベトナムなどの暖かい国の植物を育てるには、冬の養生が最も肝要である。
冬はすべて「唐むろ」に入れた方がよい。
唐室を建てるには、北が塞がって、南が開いてる場所がいい。
南側の日陰がなくて、朝から夕方まで日がよくあたるところが望ましい。
使い方
南風が吹いた時は障子を外してはいけない。
寒中、曇りの日も障子を外してはいけない
日中でも急に曇ったら、むしろをかけた方がよい
ネズミが入って草木を食べることがあるので、針金に小さな鈴をつけていけば入ることはない
春の彼岸頃より、丈夫なものからだして清明(陰暦3月、今の4月)ころにはすべて取り出したほうがよい
(出展、平野恵「もんもと人間の文化史152・温室」(法政大学出版局、2010年30~31ページ)
ヘー、凄い、丁寧なハウツーだと感心する。
だって、実践として役立つように書いているもの、概念ばかり書いて、現実(実践)のない今のハウツーとはゼンゼン違うもの…。
写真もそうなんだけど、必要になって道具が作れるようになると、自分の世界が広がってくる。
道具って、やっぱり凄い、
警備の仕事をしてよく分ったのが、僕らにとってはどうでもいいような、木片がとても重要ということ…
そう、重い柱などを仮置きする場合、ロープがすぐにかけられるように木を両端において、隙間をつくっておくの…
生活の知恵だね…
こういうことが分って一人前ということを改めて認識した(笑い)
そういう意味で、道具はまさに文化史そのものなのである