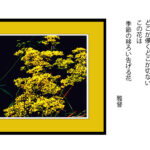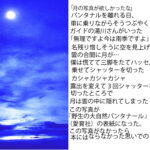目次

ベンガル菩提樹は世界で一番大きな木なのだそう
この木の枝がのびてつくる葉が、
傘となって陰をつくり涼しさを…
暑いインドでは、
その涼しさは
瞑想するに相応しい環境で、
多くの人がこの葉陰に集まって瞑想するらしい…
そうか、それでか…
菩提樹の下でお釈迦さんが悟りを開いたという意味がやっと分かった(笑い)
言葉は知っていても、
「なぜ菩提樹なの」という疑問は常にあったの…
菩提樹の木には
何か、そういうパワーがあるのかと思っていた…
だって、
菩提樹の木でつくった数珠もあるものねぇ…」
スマホカメラのお陰で楽しい想像が…
神代植物園でたまたま実を見つけ、
写真に撮って、
大型画面に写し出したら
美味しそうに見えたの…
で、
「食べられるかどうか調べよう」と思って検索かけたら、
菩提樹と瞑想の関係が分かってハハハ…
食べられるのかどうか調べてみたが、よくわからない
「その実は食べない方がいいでしょう」という記述がチラと見えたから、食べられないのかもね…

もし食べられるのであれば、
サプリメント業者が放てはおかないものねぇ…
だって宣伝しやすいもの…
「お釈迦さんもこの実を食べて悟りを開いた」とか
「不思議なミラクルパワーがいっぱい」とかね…
サンガとはサンスクリット語で「仲間・群れ」を意味するらしい
想像するに、
瞑想する人が多く集まる、
こういう場所(菩提樹の葉陰)で、
蘊蓄のある人が説教をした
お釈迦さんも、
そういう場所で説法していたのではないだろうか…
そういう処からサンガ(僧伽)というのが出来上がったのではないだろうか…
考え方によってロマンが産まれる…
そう考えると、
そこになんとなくロマンが…
「ああ 君 君…」
「君は何を求めてここにきて座っているのかねぇ…」
「ハァ…」
「ああ、いいんだいんだ 瞑想とはね求めるものnではないのだから…」
「…」
「ただ座ってね、
呼吸を整え、
自然と一体となれば
向こうから悟りはやってくる…」
なんてね…
山本周五郎の朗読(アリアさん)の中にもそんなのがあった
ある一人の武士が
岩やに籠って座禅を始めた
殿様が参勤で帰っている時に農民の一揆が勃発した
会議には昔のご学友だったその武士も呼ばれた
昔神童といわれた武士
しかし今はなかず飛ばず
殿から近況を問われ
「達磨はなぜ座り続けたのか
それが知りたくて岩やにこもり…」
「で、何かみつかったのか」と殿
「はい
壁を見ているだけでは壁に穴は開きません」
皆がどった笑った
しかし、
その人物をよく知る人は
「その言葉の中に、
秘めた覚悟を読み取った」
ことの顛末はその通りで、
すべて自分の独断で奔走し
一気がうまく収まった後
全ての責任をとって自害したその武士の墓前で、
その武士の覚悟を悟った武士から
事の顛末の説明を受けた殿は、
「そうか そうだったのか」
そう言って涙するとう物語
「見ているだけでは壁に穴は開きません」
凄いね…
心
そうだね
やっぱり腹…
覚悟だよね…
いろんなものがそうやってひとつの形になっていくの
本当に楽しい…
★
どうやら
世界一美しいとお言われる
「ヨウラクボクの花」が咲いたらしい行ってみよう…