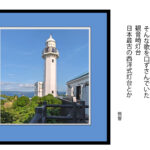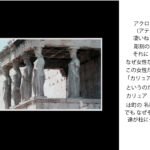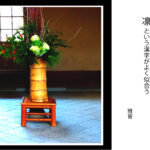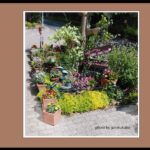目次
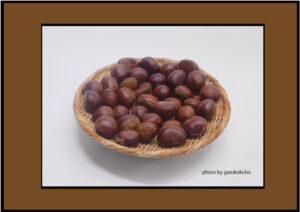
送られて来た栗 量はこの3倍くらい
栗の美味しい煮方Googleで調べたよ
早く煮るためにはやっぱり圧力鍋
僕のは五合炊き位の大きさだから
3回に分けなきゃだめだな…(笑い)
栗を美味しく煮るには下処理が大切みたい
なになに美味しい栗の見分け方
- 栗の大部分である茶色い「鬼皮」に光沢があるものがいいらしい
- 持ってみて、重みが感じられるものがおいしい栗と言われている
- 栗のお尻の部分が白くて大きいのがいいらしい
早速選別をする。
なかにはやっぱり規格外れが出てくるよね
ダメなものはその場で取り除く選別した栗は数時間水につける
理由は水につけることで皮が剥きやすくなるから(通常は一晩位)
水につけると皮が柔らかくなってナイフやハサミが通りやすくなる
水に浮く栗は栗の状態がよくないものなので、
そういう栗はNGとか
水から上げた栗はザルなどに入れ水分を飛ばす
そして
栗のお尻の方に包丁で切り込みを入れておくと、
皮が剥きやすくなる栗はよく見ると丸くこんもりした面と平べったい面がある。
皮を剥く時には丸い面を上にして、切り込みを入れたお尻から
スーッ剝くのがいいらしい
なる程
大体わかった
で圧力鍋は、
圧力がかかったら弱火にして、
圧力が自然に抜けるのを待つらしい
煮汁(塩味)の中に長時間入れることで灰汁(渋味)が抜けていいらしい。
よーしこの手順だな茹ですぎに注意と書いてあったからポイントはここだ
煮た栗は皮を剥いて冷凍しておけば保存できるので、
栗ご飯
栗がゆ
栗と銀杏の炊き込み
クリキントン
思いつくものなんでも楽しめるよね…栗とベーコンの相性調べてみると、
グッドなようなので
僕得意の簡単栗ご飯いけるね
ご飯に酒と醤油、ミリン少々入れ、
そこにベーコンを細かく切って混ぜこみ
栗を上においてラップをかけて5分間チンするだけ
仕上げにクレソンなどを添えるといいかもね…
栗はすでに水につけ、
下処理は住ませているので後は煮るだけ
ポイントは煮すぎないこだな…
いろんなところに行ってもう喋りまくっているから失敗するわけにはいかないのだ…(笑い)栗の実を
茹でて楽しむ
日曜日
今日も楽し
明日も愉し