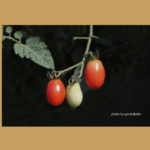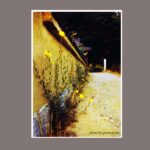目次

まさに時計 でも パッションフルーツという果物の花なの
パッションフルーツとは、時計草のことと。
その意味が知りたいのだけれど、これっというのには、なかなかいけない。
うん これならなんとか納得できるかな
その説明は
パッションという言葉から日本人は「情熱」という意味をイメージしがちですが、このパッションフルーツの場合は「キリストの受難」を意味している━と。
花の姿形が十字架に似ているということで布教にもちいたと
16世紀に南米に布教しにやってきた宣教師らが、この時計草の花をみてその花の姿形がキリストの受難を象徴する形をしている事に気づき、布教に用いたのが元になっているらしい。
そう言われれば パットと見て、真ん中に十字架があるように見えるよねぇ
そして
「パッションフラワーになる果実と言う事でパッション・フルーツと呼ばれるようになりました」
なんど読んでも、この説明が分らないない
これで説明したつもりなのかねぇ
「…」
では パッションとは
パッションの意味は情熱。
パッションフラワー 、情熱の花といことか、
なる程、そこにキリスト教の意味をムリムリ持たせようとするからややこしんだね。
よしわかった 自分流で解釈すると
16世紀 南米で布教していた宣教師がこの花を発見した。
南米で見たこの花(もしかしたら真っ赤な実だったかも知れない)が、情熱という意味から考えるとやっぱり実だな。
真っ赤な実を見て 情熱的に見えたので、
「これは」と地域の人に尋ねると、
時計のような花を咲かせるということが分かった。
それで、赤い実をパッションフルーツ
その実をつける花をパッションフルーツフラワーと呼んだ。
ところが、多くの人が、この花を見て時計草と呼んだので、
それで
パッションフラワー=時計草となった
そういうことではないだろうか。
こういうところで説明する場合、
一般的に意訳というのをきらう傾向にあるらしい。
しかし、翻訳に関しては、意訳こそ翻訳と僕は思っているので、意味のない言葉を羅列されても、理解できないのだ。
うん そう、やっぱり 翻訳家といわれる人たちの翻訳はすごい、だって文学だもの
こんなことを書くと、
「お前 何いってんだバカ」といわれそうだね(笑い)
でもやっぱりねぇ
「ああ そうだったのか」と感動させるように伝えてくれなければねぇ
今日もまた分けのわからないことを書いてしまった。
時計草 パッションフルーツフラワーについて書きたかったんだけど、
検索の力不足で、いやはやなんとも…
検索の方法 何かいいのがあったら教えてください