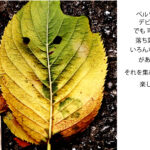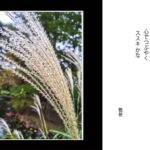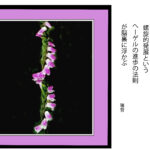目次

漢字難しいねぇ初めてみたよ雨に鶴なんて…
しかし
この字「靏」
ツルとしか読めないので
手書きアプリというのに雨と書いて
その下に「鶴」と書いたら「ツル」と
初めてみたよこんな「靏」
だけど
なんで雨+鶴なんだろうねぇ
遊び半分で調べてみると
「私もよくは分かりませんが・・・」
そう前置きをして
「鶴の元字です。
漢字が象形文字・甲骨文字・金文・篆書等から中国で最初に漢字になったときには 、
つるは?と書いていたみたいですよ、
江戸時代には使われていたのではないでしょうか」
という書き込みがあった
丁寧にも
参考にと
http://edomakyou.seesaa.net/
が貼られていたので開けてみると
「(江戸柄鏡を収集)をしていますが、
所持している
(?文字入り柄))は8面に全て雨かんむりの(?の文字)が入っております。
雨かんむりのない「鶴の文字」の柄鏡が1面もなく、
なぜ全てに「雨かんむり」がついているのか?良く解りません。
漢字に詳しい方、歴史好きの方、お調べの上、是非お教え下さい」と…
いろんな人がいるねぇ…
思うに
ツルという字
元は「靏」だったんだろうね……
ついでだから「雨」という字の成り立ちを調べてみると
「大気中の水蒸気が冷えて雲ができ、雲の中で大きくなった水滴が地上落ちててく現象を表わした象形文字(漢字/漢和/語源辞典)」とか
さらに雨の名前を調べてみると
霖雨(りんう)
地雨(じあめ)
霧雨(きりさめ)
豪雨(ごうう)
篠突く雨(しのつくあめ)
俄雨(にわかあめ)
肘傘雨(ひじかさあめ)
驟雨(しゅうう)
凍雨(とうう)
梅雨(ばいう)
五月雨(さみだれ)
夕立(ゆうだち)
氷雨(ひさめ)
秋雨(あきさめ)
時雨(しぐれ)
春雨(はるさめ)
菜種梅雨(なたねづゆ)
虎が雨(とらがあめ)
半夏雨(はんげあめ)
寒九の雨(かんくのあめ)
村雨(むらさめ)
叢雨(むらさめ)
怪雨(あやしあめ かいう)
外待雨(なまちあめ)
走り梅雨(はしりづゆ)
送り梅雨(おくりづゆ)
戻り梅雨(もどりづゆ)
空梅雨(からつゆ)
山茶花梅雨(さざんかつゆ)
村時雨(むらしぐれ)
いっぱいあるねぇ…
昔の日本の人の感性やっぱり凄い
日本人の心意気というかねぇ…
微妙な自然の綾を愉しむというか…
昔の人は、
そういう感性に勝れていたんだね…
で、
何で靏が雨を被っているのか…
これ━という答えはみつからなかったが、
スマホカメラのおかげで結構楽しめた
スマホかめら本当に楽しい