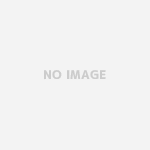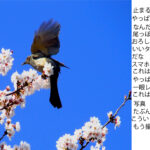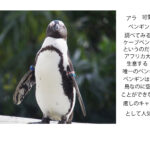目次

新宿は、その昔、「内藤新宿」という宿場町。
新宿とは、「甲州街道」に追加で設けられた新しい宿場という意味。
もともとは、甲州街道の第一宿は、日本橋から4里の「上・下高井戸宿」だった。が、
1698年(元禄⒒年)に日本橋から約2里の「内藤新宿」に形成された宿場町なのだそう。
なる程、「新宿」とは、新しい宿場という意味だったのか。
字を読めばそうだけどね、知らなかった(笑い)
ところで、なぜ「内藤」?
新しい宿「新宿」の上に「内藤」という冠がついているのは、
新宿という宿場が、内藤氏が幕府に返上した屋敷地に置かれたから。
内藤家とは
今、国立公園となっている新宿御苑は、内藤家の屋敷があった場所で、公園になったのは、1906年(明治39年)から。
内藤家は信州の大名。
藩祖の内藤清成が家康から、現在の新宿御苑にあたる広大な土地を拝領し、江戸下屋敷として幕末まで保有していた。
信州高遠藩は、保科家(二代)に始まり、鳥居家二代を間に挟み、内藤家八代(幕末まで)が藩主をつとめている。
内藤トウガラシは、そこで(新宿御苑)で作られていたトウガラシらしい。
内藤とうがらしは、葉の上に房状の実をつける八房(やつふさ)系と言われる種類のトウガラシで、鷹の爪よりも辛みが優しく、食べやすく、上品な旨みと爽やかな風味を感じることができるのが、特徴とか。
「旨みを増強する呈味(ていみ)成分が豊富で、だしに使うと、より他の食材の美味しさを引き出します」という記述もあった。
見るからになんとなく、優しい、そんな感じがするよね、この(写真)のトウガラシ。
このトウガラシ(内藤トウガラシ)
葉とうがらし・青唐辛子・赤唐辛子と、順に変化していくところを楽しむことができるということで、園芸種としても人気になっているみたい。
味の特徴は、
極端に辛すぎず、ピリッと優しい味わい。
「食べた瞬間に刺激的な辛さがくるわけではなく、後からじんわり辛みが広がるので、辛いものが苦手な方でも食べやすい」らしい。
香りと旨みがたっぷりの青トウガラシ 赤トウガラシは、
青唐辛子は爽やかな香りと苦味のある辛さ、
赤トウガラシは、
「豊かな香りと熟成された旨みを感じることができる」とも。
葉っぱも美味
他と比べて葉っぱが大きく柔らかい。初夏のまだ葉が硬くならないうちに収穫すれば、葉唐辛子としてさまざまな料理に使えるらしい。
こんな記事もあったよ。
僕もこれ買って、何かつくって見よう。
昨日、お皿も貰ったし(笑い)