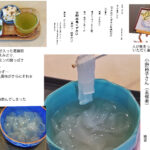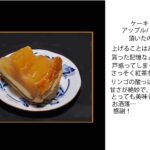セルフポートレート
なんとなく哀愁が漂ってるねぇ…
いつまでそんなことをやってるん
いい齢をして…
バカだよねぇ…
こんなことをして毎日
もう
70を超えてるんだぜ
そうだよなぁ…
でも他にすることないし…
そんなに毎日毎日写真を撮ってどうすんだよ…

確かに
でも、はたからみればそうかも知れないけれど
これが僕の生き甲斐なんだよ…
風を感じ
空気を感じ
色を楽しみ
山河を愉しみ
花や風景や
光りや音…
それをいかにしてビジュアルにしようかと…
そして僕の心は
この時何を感じたんだろうと考えるのが楽しいの
で、
その考えたことを、
いや違う
帰って写真も見ていたら
勝手に指が動いて何か書いてくれるの、
決して飾らない
けっして考えない
ただひたづらに思い浮かんだことをタイピングするの
それを読むのがまた楽しくてねぇ…
人にはそれぞれの価値がある
エッ何…
そんなことをして何になるのかって、
ハハハ
そうだよね…
でもね、
最近はSNSというのができて、
発表すればそれが読んでもらえるし、
それでいいねなんてくるとね、
とても楽しいの…
そこから色んなエネルギーの回転が始まるの
そしてそのブログから、
いろんな人、
しかも世界中の人との交流がうまれ、
それがまた楽しいんだよねぇ…
ブログ、SNS、そして今は出版コードも手にいれた
自分で書いた本を 自分で編集して
世界のマーケットで売れるんだよ
こんな社会が来るなんて
想像もしてなかったよ
だから、
あてもなく歩いて彷徨っていることも、
何にもならないわけではないんだよ…
で、
おまえそれでいくら稼げるんだよ…
さーねぇ…
わからないねぇ…
でもそんなことはどうでもいいじゃん
警備の仕事、
立ってりゃお金もらえるんだし…
健康で元気ならば80歳をこえても働けるんだよ…
ありがたいよねぇ…
でも一つだけ言えることは、
いずれ体も衰弱して働けなくなる
その時どうするかということは考えておかなければ…
瞬き10年の年代だから…
夢や希望だけでは飯は食えないから…
うん
これは切実な問題だ…
取りあえず今日は仕事
明日考えよう…
今日も愉し
明日も愉し
でもね、
自分が考えていたことが少しづつ形になってくことが、とても楽しい
のである