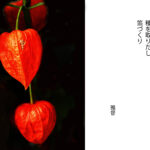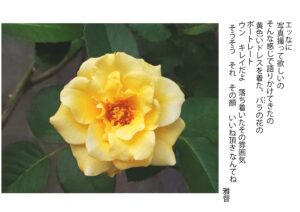
写真は顔写真に始まって顔写真に終わるなんて、昔、よく言われたの
だって仕事の大半は人物写真を撮ることだったから…
そう、インタビューアと一緒に行って、
インタビューをしている最中に、横にいて、写真を撮るの
記事中の写真もあれば、表紙の撮影もある
アンブレラのストロボを一灯持って行ってね…
本当に本当に本当に随分の人の顔写真撮ったよ、
そういう中で一冊だけ本になっているの
「宇宙の渚で生きるということ」(海象社)
この本は、「月刊省エネルギー」(財団法人省エネルギーセンター)に約7年連載された
(時世の地平線を再編してつくられたもの)
各界で活躍している文化人、著名人を一同に集めたもの
今見返しても懐かしい…
そのエピローグを、なんと僕が書いているのである
抜粋して紹介すると
「写真家の仕事は、顔写真に始まり顔写真に終わる」という先輩たちのいうとおり、顔写真というのは実に奥の深いものだ。
写真家になって数十年、私が見つけたポイントは、「目」だった。
アクションが派手に決まっていても、目が活きてなければ感情は伝わってこない。いわゆ「いい顔にならない」のである。
だが、目が活きていればアクションがなくても活きた写真になる。だから人物を撮影する時には、
心を無にして、相手の目に意識を集中してシャッターを押すのが私の体得した撮影術である…」
こんなことを書いているのだが、
目というのは、やっぱり大切で、思いは今も変わっていない
僕にとって花の写真もその延長線上にあるわけだから、ポイントを見つけたらそこに意識を集中して…
写真というと、
なぜか皆、構図とかと、すぐ言うのだけれど、
僕はそんなの意識したことは一度もない
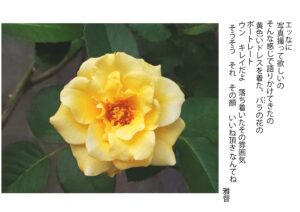
絵画は足し算で写真は引き算、
まして写真にはフレームがあるのだから、いいと思ったらそのように撮ればいいと僕は思っているから…
サージの法則だとか、いろいろいうけれど、
現場に行って、
そういうもの意識して撮れるのかねぇ…
「写真なんて、ボーンと前に行って、ボーンと撮ればそれが一番」というのは、ある有名カメラマンの言葉なのだが、僕もそう思っているのである。
写真は楽しい、
何はともあれ、
楽しんで撮るのが一番と僕は思っているのである