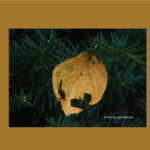目次

芙蓉、夏を代表する花だと思う。
早朝、生まれた間もない明るい太陽に照らされて、鮮やかに咲く大輪の花…
美しくて、つい、目を奪われる。
朝に咲いて夕方には萎む、その儚さが、一層、美しさ誇張しているのかも知れない…ね。
芙蓉と酔芙蓉の違い
同じような花で、朝に純白の花を咲かせ、夕方になるにつれてピンクに染まっていく酸芙蓉というのがあるが、夏芙蓉と酸芙蓉、何が違うのかと思って調べてみると、
一重の花と八重の花で、
一重に咲くのが芙蓉で、八重に咲くのが酔芙蓉なのだそう。
古代中国では、蓮の花を芙蓉と言っていたらしい
「芙蓉」とは、蓮の花の古名で、その美しさから、「芙蓉の顔」と書いて「ふようのかんばせ」という言葉があったのだとか。
「ハスの花のように美しい」という形容詞らしい。
第一高等学校の寮歌「嗚呼玉杯に花うけて」の2番に
「芙蓉の雪の精をとり 芳野の花の華を奪い…」という歌詞がある。
富士山は芙蓉峰という雅称を持っている
この芙蓉は、多分、富士山のことだと思う。
そう、富士山は「芙蓉峰」という雅称を持っているのである。
雅称とは、風雅な呼び方のこと。
ということから、考えると、
富士山の雪のように白く、芳野の桜の花のような香りを放つ。
それ程美しい花ということではないだろうか。
室町時代から、貴族の間で、人気があったことが推測できる…
これは、勝手な解釈だけどね…