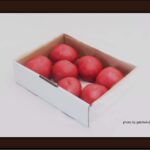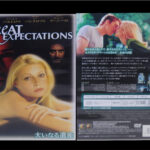目次

写真、無茶もテクニック いいと思えばそれでいいのだ
昨日、夕方、深大寺へ。
バスを降りたら、太陽が、つるべ落しの真っ最中。
持っていたカメラは、おもちゃみたいなコンデジ・
太陽を正面に受けると、露出のコントロールは不能で、何んの役にもたたない。
しかし、習癖、本能がシャッターを切らす。
モニターを見ると、太陽が見えるだけ。
それでもガチャガチャと適当に動かして何枚かシャッターを切る。
そのデータをコンピュータに出し、トーンカーブで調節したのが、今日の写真。
写真、無茶もテクニックなんて、もう、ハチャメチャなんだけど、惹かれるものがあって、
「よし、今日はこれで」となったわけ
で、写真を見ていて、さて何を書こうかと、ワードプレス立ち上げて出てきたのが、
「無茶もテクニック、いいと思えば、それでいいのだ」
というフレーズだったの。
で、今は、
そのフレーズをキーワードにして、これから、どうやってそのフレーズに文章を足していこうかと思いながらキーボードをたたいているの(笑い)
実は毎回、僕はそうやって記事を書いているんだけどね…
書きながら、意識の何処か、いつも渦巻いているのが、
「写真にかくあるべきという法則はない」ということ。
そう言うと、ちょっと問題があるな…
そうだな、
プロ(職業写真家)として撮る場合には、クライアントに納得してもらわなければならないわけだから、無難に確実に、キッチリとした写真を撮らなければならないが、今、言っているのは、楽しみとして写真を撮る時のこと…
つまり、大袈裟に言えば、作家としての作品づくりをする場合のことで、
そこには、「斯くあるべし」というものは何もないのである。
そう、自分がいいと思えば、それでいいのだ。
僕の概念でのアーチスト像
ただし、自分がいいと思っても、人が同じように感じてくれるかどうかというのは、また別の話…
いわゆる作家の人たちというのは、自分の世界を発表して、多くの人の心を捉えているのである。
僕の概念ではアーチストとはそういう人たちのことなのである。
ところが、最近は、昔流に言えば
「カメラを買えばカメラマン、鉛筆買えばルポライター」
これは、僕が駆け出しの頃に言われた言葉だけど、まさにまさにまさになった。
言い換えれば、その頃言われた「軽薄短小」がますます進んでいるのが昨今、そんな気がしているのは、世の中の流れになかなかついていけない、年寄りの愚痴か…
★ ★
しかし、(だが、ここでそういう接続しがいるのかどうかは疑問だが、これがないと、話の切り替えができないので、合いの手として、ところでという意味かな)
そういう時代にコンテンポラリーフォトグラフィーという手法が流行して、僕も、熱病にかかったように傾倒したのだが、
簡単に言えば、
「意識的欠陥写真」(コンテンポラリーフトグラフィー)
きれいじゃないから伝わるものがある。
はちゃめちゃだから伝わるものがある。
ボケているから、より感じられる
そんな概念で、意識を表に出す(ビジュアル化する、表現としての写真)の時代がやってきて、本当に楽しかった。
昨日、撮った、この写真を見ながら、コンテンポラリーの頃のことがフと思いだされたのである。
そして思ったのが、
デジタルカメラで、それをやると、面白いかもしれないということだった。
だって、ブログのタイトルが
「撮って書いてワヤで笑える人生日記」だもの。そういう生き方をしな、ければ…ね(笑い)