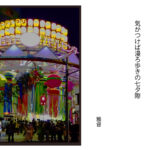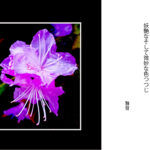目次

逆光で蕾がキラキラと輝いていたの。
しかし、
これ、
結構難物で、
正直言って、
どう撮ってよいのか分からなかったから、
コンデジのズームをいっぱいに効かせて撮ってみたの。
多分300㎜(35㎜換算で)位だと思う。
そういうのが僕にはよく分らないの、
メカに弱くて、
カメラは写ればいいと思っているから、
それにこのカメラ、
もはや製造中止の古いカメラなので、
どういうレンズが着いているのか、
それすら忘れているのだから(笑い)
望遠は、
画面をパターン(平面的図案)にしてくれるので、
それが面白くてね…
若い頃には、
超ワイドで、
パースペクティブ(遠近感を強調した写真)の面白さが好きだったんだけれど、
今は、
なぜか分からないけれど、
パターン化した平面の風景ばかりを撮っている
そんな気がする。
面白いよね、
望遠レンズ…
じーと見ていると、
リズムがあって、
とても楽しそう
うん、
急に暖かくなったから、
花も浮れているんだね…
しかし昨日は雨…
春先には必ず起こる三寒四温
三日寒い日が続くと、
四日暖かい日が続くという現象
昨日、
知合いの若い女性に
「寒いね、三寒四温だね」
と言ったら
「向こう三軒なんとかというのと一緒」と、
「違う違う、全然違う」
そう答えてから、
「三日寒いと…」
そんな説明をしたのだが、
説明しながら、
「なぜ、そういう現象が起きるのか」とフッと思ったので、
調べてみた。
「三寒四温」という言葉
もともとは、
中国の東北部や朝鮮半島北部で使われていたらしい。
本来は冬に起こる現象なのだが、
最近は春先の現象となっている。
なぜ、
そういう現象が起きるのか
それは、
通り過ぎる低気圧がもたらすらしい。
説明によると、
基本的に西から東に向かって低気圧と高気圧が次々と流れてきて、
低気圧が伸びる2本の前線の間に暖かい空気があって、
外側には冷たい空気がある。
これが1週間位のサイクルで繰り返されながら春に近づくにつれ、
暖かくなっていく。
それを三寒四温と、
三寒四温 簡単に言えば
きっちり説明しようとすれば、
そういうことになるらしいが、
簡単に言えば三寒四温とは、
西から東に低気圧が流れていくため、
温かい空気と冷たい空気が交互にやってきて起こる現象ということらしい
アー疲れた(笑い)
ついでながら、
三寒四温は春の季語ではなくて冬の季語なのだそう。
そりゃそうだよね、
三寒四温を繰り返して春になっていくのだから…
それにしても昔の人は凄いね
最近の新語とは全然違う…
そう言えば、
最近は、イケメンの反対、
ダサい男のことヌマというらしい
説明を聞くと
「池」と「沼」というこたえが…
思わず笑ってしまった